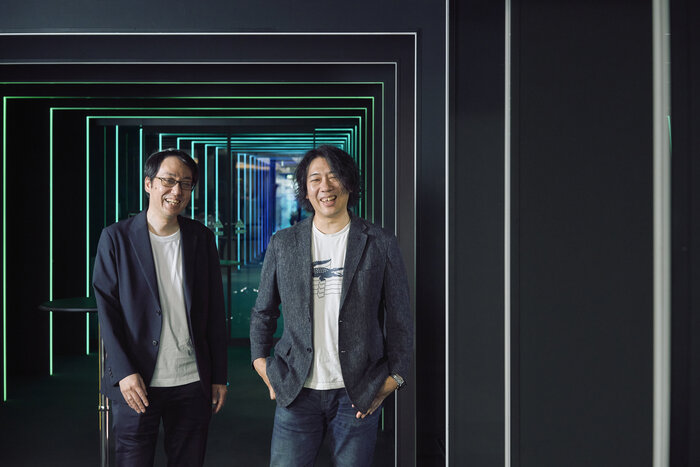有望な重点領域を特定し、事業部門のベンチャー企業との協業立ち上げを支援する
株式会社NTTデータ オープンイノベーションチーム




2013年から、社内事業部門と外部企業との協業ビジネス立ち上げ支援を行っている、株式会社NTTデータオープンイノベーションチーム。
広範な領域に及ぶ、100以上の事業部を5人のメンバーで支援し、事業創出を行う上で、どのようにスピーダを活用いただいているかを、オープンイノベーションチーム 藤原 健一 様にお伺いしました
サマリー
- ・産業の定義が十分成り立っていない領域についても必要な情報がすぐ手に入る
- ・活用例①:フォーカスエリアを定めたい事業部のニーズに対する勝ち筋の分析
- ・活用例②:お客様からの課題に対して足りない情報をピンポイントにカスタムリサーチで収集
オープンイノベーションチームのミッションや役割について教えてください。
顧客の潜在的なニーズを理解し、その理解に基づいてイノベーション機会を積極的に創出する役割を持っています。
以前はビジネスコンテストを開催し、その中で「Catch&Go」(デジタル店舗運営サービス)など、顧客との協業ビジネスの機会を多数創出しました。
コンテストはビッグデータ、AI、5Gなどの分野で有望な企業や技術を見つけるのに役立ちましたが、年に一度しか開催されなかったため、発見を基に新たな協業ビジネスをタイムリーに展開する上では課題がありました。
そこで現在はイベントドリブンというよりも、社内の事業部のニーズに合わせて、スタートアップに限らず中堅・大手企業も含む外部との協業ビジネスの立ち上げ支援を行っています。
協業ビジネスの立ち上げ支援では、まず社内の事業部(現在は100以上ある部門の中から40程度に絞り込んで実施)へのインタビューを行っています。
その声を通して顧客ニーズをよりよく理解し、イノベーションの重点領域を具体的に絞り込む調査を行い、パートナーを探索し、協業の立ち上げに進んでいきます。
どのようなシーンで、スピーダを活用いただいていますか。
私たちはそれぞれ得意領域を持つ5人のメンバーで事業部の支援を行っていますが、その領域は多岐に渡るため、私たちチームも広範な分野で専門的かつ最新の情報を必要とします。例えば、金融業界のクライアントに信頼されるITサービスを提供するためには、そのドメインの新興技術やビジネストレンドを包括的に理解している必要があります。(BNPL(後払い)、デジタルバンキング、ウェルネスマネジメント、DeFi(分散型金融)、ブロックチェーンなど)
そこで、効率的にビジネストレンドを把握し、各ドメイン内の成長機会を特定するための新しい解決策が必要でした。
スピーダ イノベーション情報リサーチは、産業の定義が十分成り立っていない領域についてもレポートを作ってくれるので、変化の早い時代でも、ビジネストレンドを把握したガイダンスを行うために必要な情報がすぐに手に入ります。
そもそもセグメントの言語化に悩む場合にも、Industry一覧から、「こういう切り口もあるのか」「こういう方向性もあるのか」という発見をすることもあります。
また、協業パートナー開拓のための調査にも活用しています。
特に印象的な活用例があれば教えてください。
1つは、インダストリーレポートを使い、フォーカスエリアを定めたい事業部のニーズに対してどこが勝ち筋なのかを分析した例です。
フードテックビジネス創発をしたいという事業部から、情報提供してほしいという相談を受けました。
まず、フードテックの動向を掴み、サブセグメントから有望な市場を特定し、さらにその中で、どこにビジネス機会があるかといった調査を効率的かつ効果的に行うことができました。
もう1つは、カスタムレポートを利用してお客様からの課題に応えた例があります。
課題に対して「何が足りない情報なのか」を考え、ピンポイントに知りたい情報を、カスタムリサーチを使って収集できました。
そこからレポートのファクト情報と照らし合わせて、仮説の信憑性を高め、検討を一歩先に進めることができました。
今後、取り組みたい挑戦や課題はありますか?
ビジネス立ち上げの成功確率を高めることは永遠の課題です。
今日は、情報を集める話をしましたが、最終的な目的はビジネスをつくること。
自分達の戦略を検証する際に、我々の主観として「ここがいいんじゃないか」というようなインサイトを導き出して検証に入れるような、主体的にフォーカスポイントを選定することができるようにならないといけないと思っている。
そのためには、イノベーションテーマを継続的かつ効率的に獲得し、いかに自分達の仮説に繋げられるかがポイント。
イノベーションの文脈には、インダストリーとテクノロジーがあるが、これらをどのように組み合わせてビジネスを作ってマネタイズしていくのか、ここに我々の存在価値があると思っています。